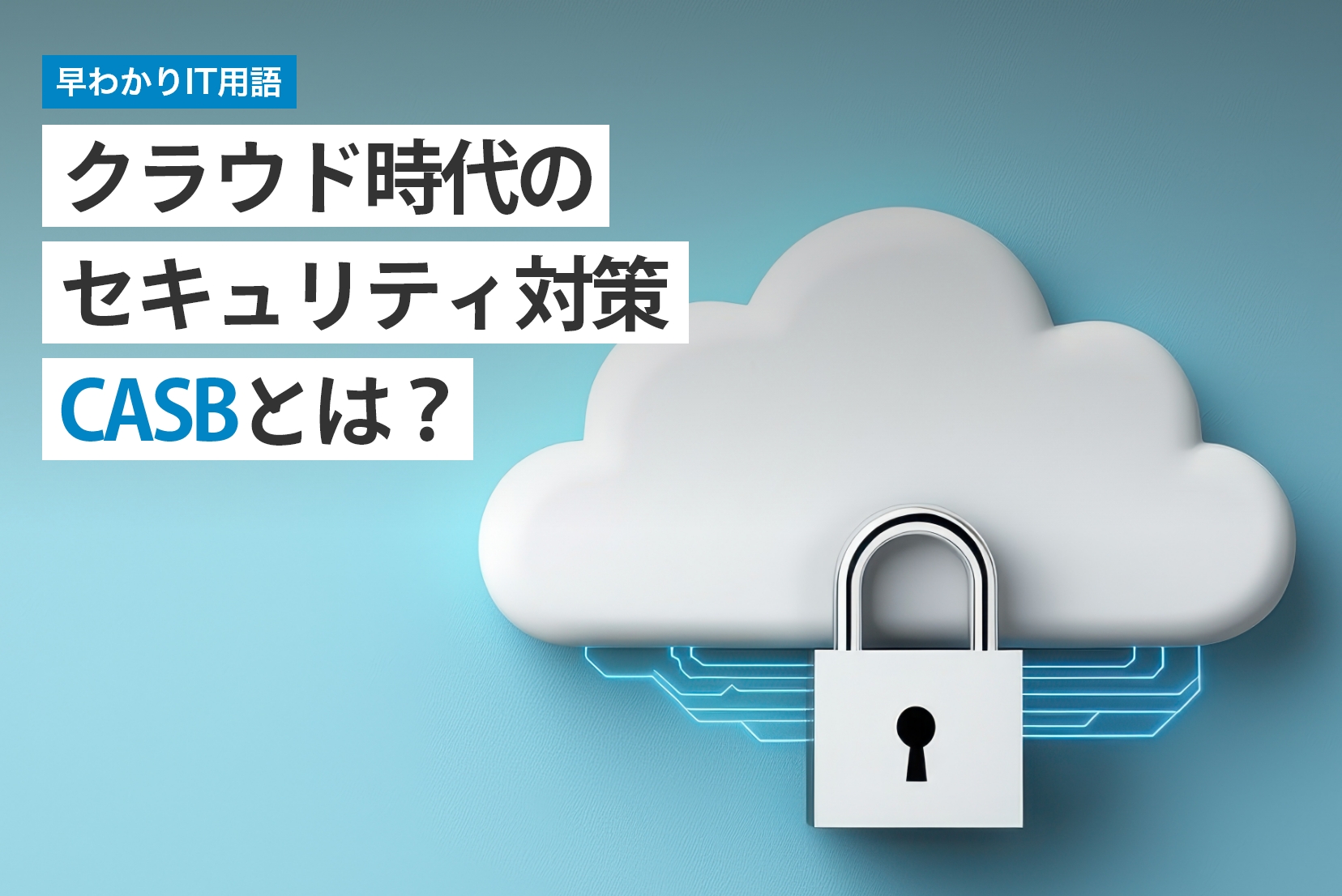インシデントレスポンスとは?実践に役立つ基礎知識と5つのステップ

インシデントレスポンスとは、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントが発生した時の対応プロセスのことを指します。企業においては、情報資産を守るための重要なプロセスであり、欠かせないものです。この記事では、インシデントレスポンスの基本的な知識と、実践に役立つ5つのステップについて詳しく解説します。基礎を知ることで、迅速な対応体制の構築や情報共有の改善、リソースの最適化を図ることが可能になります。最新の情報と技術を駆使し、効果的なインシデントレスポンスを実現しましょう。
- インシデントレスポンスとは、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントが発生した時の対応プロセスや活動のことを指します。
- インシデントの検知、特定、封じ込め、根絶、復旧、報告とレビューのステップがあります。
- 情報漏洩やランサムウェアなどのサイバー攻撃が増加する現代において、迅速な対応が求められるため、対応策を事前に準備しておくことが必要です。
-
 Tech Tips編集部
Tech Tips編集部富士ソフト「Tech Tips」編集部です。トレンドのIT用語をわかりやすく解説しています。
インシデントレスポンス(incident response)の基礎知識

インシデントレスポンスは、セキュリティ被害を最小限に抑え、迅速な復旧に貢献します。実現するためには、セキュリティインシデントを想定して、適切な準備と専門チームの編成など組織的な取り組みが必要です。また1年に1度はインシデントが起きたことを想定したシミュレーション訓練を行い、準備をしておくことも大切です。
インシデントレスポンスの定義と目的
インシデントレスポンス(incident response)とは、セキュリティインシデントが発生した際に、迅速かつ効果的に対応するための一連の手続きや活動を指します。これには、インシデントの検知、特定、封じ込め、根絶、復旧、そして報告とレビューが含まれます。インシデントレスポンスの目的は、企業のデータやシステムを保護し、ビジネスの中断を最小限に抑えることにあります。特に、情報漏洩やランサムウェアなどのサイバー攻撃が増加する現代において、迅速な対応が求められます。
インシデントレスポンスとサイバーセキュリティの関係
サイバーセキュリティは、情報システムやネットワークを保護するための総合的な取り組みを指し、その中でインシデントレスポンスは、実際にインシデントが発生した際の具体的な対応策を提供します。これにより、被害を最小限に抑え、迅速な復旧を可能にします。サイバーセキュリティとインシデントレスポンスは、相互に補完し合い、組織の安全性を高めるために不可欠な要素です。
セキュリティインシデントとは
セキュリティインシデントとは、情報システムやネットワークにおいて、セキュリティポリシーや標準的なセキュリティ手順に違反する出来事を指します。これには、データの不正アクセス、情報漏洩、サービスの中断、システムの不正利用などが含まれます。
インシデント対応とは
インシデント対応とは、情報システムやネットワークにおけるセキュリティインシデント発生時に、迅速かつ効果的に対応するプロセスを指します。これには、インシデントの検知、影響の評価、被害の最小化、復旧作業、再発防止策の策定が含まれます。
インシデントレスポンスに必要な5つのステップ

インシデントレスポンスを効果的に実施するために必要な5つのステップを詳しく解説します。企業や組織が迅速かつ適切に対応し、被害を最小限に抑えることを目指します。特に、ITセキュリティ担当者や経営者にとって、これらのステップはリスク管理の基盤となるでしょう。
1. 準備(Preparation)
準備段階では、計画の策定とチームの編成が行われます。これには、ポリシーの設定、役割と責任の明確化、必要なツールやリソースの確保が含まれます。また、定期的なトレーニングやシミュレーションを通じて、チームの対応能力を高めることが重要です。
2. 検知と特定(Detection & Identification)
このステップでは、インシデントの早期検知と特定が求められます。セキュリティ監視システムを活用し、異常な活動や不正アクセスを迅速に発見することが重要です。検知されたインシデントは、影響範囲や深刻度を評価し、適切な対応策を講じるための基礎情報として活用されます。早期の検知と特定をすることで被害の拡大を防ぎます。
3. 封じ込め(Containment)
封じ込めの段階では、インシデントの影響を最小限に抑えるための措置が講じられます。具体的には、感染したシステムの隔離やネットワークの分断、アクセス制御の強化などが含まれます。被害が他のシステムやデータに波及するのを防ぎ、迅速な復旧に貢献します。
4. 根絶と復旧(Eradication & Recovery)
根絶と復旧のステップでは、インシデントの原因を完全に排除し、システムを正常な状態に戻す作業が行われます。マルウェアの除去や脆弱性の修正、データの復元などが含まれます。また、復旧後には、再発防止策を講じることが重要です。これにより、同様のインシデントが再び発生するリスクを低減します。
5. 報告とレビュー(Reporting & Reviewing)
最後に、インシデントの詳細な報告とレビューが行われます。これには、インシデントの経緯、対応の評価、改善点の特定が含まれます。報告書(インシデントレポート)は、今後の計画改善に役立ちます。また、関係者への情報共有を通じて、組織全体のセキュリティ意識を高めることも重要です。
インシデントレスポンスに必要なツールと技術
ツールはインシデントの検知や分析、対応を支援し、技術はこれらのツールを効果的に活用するためのスキルを提供します。特に、ITセキュリティ担当者や経営者にとって、これらの要素を理解し、適切に導入することは、組織全体のリスク管理において重要な役割を果たします。
セキュリティツールとサービス例
インシデントレスポンスにおいては、さまざまなツールが活用されます。例えば、SIEM(Security Information and Event Management)ツールは、リアルタイムでセキュリティイベントを監視し、異常を検知するのに役立ちます。また、EDR(Endpoint Detection and Response)ツールは、エンドポイントでの脅威を検出し、迅速に対応するための情報を提供します。これらのツールは、インシデントの早期発見と迅速な対応を可能にし、被害を最小限に抑えるために重要です。
インシデントレスポンスに求められる技術スキル
インシデントレスポンスを効果的に行うためには、専門的な技術スキルが求められます。まず、ネットワークセキュリティの知識は不可欠であり、ネットワークトラフィックの分析や異常検知に役立ちます。また、デジタルフォレンジック調査は、インシデントの原因を特定し、証拠を収集するために重要です。さらに、スクリプト言語の知識は、ツールの自動化やカスタマイズに役立ちます。これらのスキルを持つことで、インシデントに対する迅速かつ効果的な対応が可能となります。企業内でセキュリティ人材が不足している場合は、マネージドセキュリティサービスをご検討ください。富士ソフトではお客様のセキュリティ構築および運用を総合的に引き受けるサービス「FujiFastener」を提供しています。
インシデントレスポンスの運用体制とチーム構築ポイント

インシデントレスポンスの運用体制は、企業がサイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントに迅速かつ効果的に対応するための基盤です。適切な運用体制を整えることで、被害を最小限に抑え、企業の信頼性を維持することが可能です。運用体制を構築する際の重要なポイントと、効果的なチーム構築の方法について詳しく解説します。特に、ITセキュリティ担当者や経営者が知っておくべき情報を提供し、実践に役立つ知識を深めます。
シーサート(CSIRT)とは
シーサート(CSIRT)は、企業や組織内で発生するセキュリティインシデントに対処する専門チームです。インシデントの検知から分析、対応、復旧までのプロセスを管理し、被害を最小限に抑えることを目的としています。シーサートは、技術的なスキルを持つメンバーで構成され、各自の専門分野に応じて役割を分担し、迅速かつ効果的な対応を行います。これにより、被害を最小限に抑え、再発防止策の検討などを行い、企業の信頼性を守ります。
チーム構築で留意すべきポイント
チームを構築する際には、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。まず、チームメンバーの選定です。技術的なスキルだけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力も重要です。また、チーム内での役割分担を明確にし、各メンバーが自分の役割を理解していることが重要です。さらに、定期的なトレーニングやシミュレーションを行い、チームの対応力を向上させることも欠かせません。実際のインシデント発生時に迅速かつ効果的に対応できる体制を整えましょう。
ランサムウェア攻撃からの復旧を早めるためのポイント

ランサムウェア攻撃を受けた場合、数日で復旧する企業もあれば、1カ月近く時間がかかるところもあります。その違いは、セキュリティ対策に「軽減」の考え方があったかどうかです。復旧が早い企業は、おそらくランサムウェアによる攻撃を受けることを前提として、被害を軽減する考え方でシステムを構築しています。インシデントが起きた時の対応プロセスであるインシデントレスポンスを定めている企業は、速やかに普及して被害規模を最小減に抑えられます。しかし日本でインシデントレスポンスを定めている企業は、まだまだ少ない状況です。被害の軽減ではなく、そもそも侵入されないための「防御」の考え方だけでは、いざ侵入された時の対策が後手に回ってしまい、被害が拡大していきます。インシデントレスポンスを定めておくことは復旧を早めることに繋がります。
インシデントレスポンスの導入前に知っておきたい注意点
インシデントレスポンスの導入は、企業のセキュリティ体制を強化するために不可欠です。しかし、導入前にはいくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。効果的なインシデントレスポンスを実現し、組織全体のリスクを最小限に抑えることを目指しましょう。導入前に知っておくべきポイントやよくある失敗を回避する方法について詳しく解説します。
導入前に整理すべきポイント
インシデントレスポンスを導入する前に、まずは組織内のセキュリティポリシーを明確にすることが重要です。これには、情報の分類やアクセス権限の設定、データの保護方法などが含まれます。また、インシデント発生時の対応フローを事前に策定し、関係者全員が理解していることを確認することも必要です。さらに、適切なツールや技術を選定し、導入後の運用体制を整えることが求められます。
よくある失敗とその回避方法
インシデントレスポンスの導入においてよくある失敗の一つは、計画の不備です。計画が不十分だと、インシデント発生時に迅速な対応ができず、被害が拡大する恐れがあります。これを回避するためには、事前にシミュレーションを行い、計画の実効性を確認することが重要です。また、情報共有の不足も失敗の原因となります。社内での情報共有を徹底し、全員が最新の情報を把握できるようにすることを徹底しましょう。
インシデントレスポンスを効果的に行うための社内研修・教育の重要性
インシデントレスポンスを効果的に行うためには、社内での研修や教育が不可欠です。インシデント発生時に迅速かつ適切に対応するための知識とスキルを持つことは、企業のリスク管理において重要な要素となります。実践的なトレーニングは、組織全体のセキュリティ意識を高め、インシデント発生時の対応力を向上させます。
また、社内研修を通じて、インシデントレスポンスの最新技術や情報を共有することは、迅速な対応体制の構築に寄与します。情報共有の不足やリソースの不足といった課題を解決するためには、継続的な教育とトレーニングが必要です。外部支援の活用も視野に入れつつ、社内での教育を強化することが、効果的なインシデントレスポンスの実現に繋がります。
インシデントレスポンスの全体像と押さえるべきポイント
インシデントレスポンスは、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントに対する組織の対応プロセスを指します。標準的なインシデントレスポンスのフェーズには、準備、識別、封じ込め、根絶、回復、および教訓が含まれます。インシデント発生時には、情報が適切に共有され、迅速に対応できる体制が必要です。また、専門知識を持つ人材やツールの不足を補うために、トレーニングや外部支援の活用が重要です。最新の情報と技術を常に把握し、組織全体のセキュリティを強化することが求められます。
今後の展望

インシデントレスポンスの未来は、技術の進化とともに大きく変わることが予想されます。AIや機械学習の導入により、インシデントの検知と対応がより迅速かつ正確になるでしょう。これにより、企業はより効率的にリスクを管理し、セキュリティインシデントの影響を最小限に抑えることができるようになります。しかし、サイバー攻撃は日々手口が複雑化し、攻撃の回数も増大しています。侵入された時の「軽減」対策として、インシデントレスポンスを導入し、いざという時に備えましょう。富士ソフトではセキュリティの専門家が多数在籍し、お客様の環境に合わせた最適なセキュリティ対策をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。