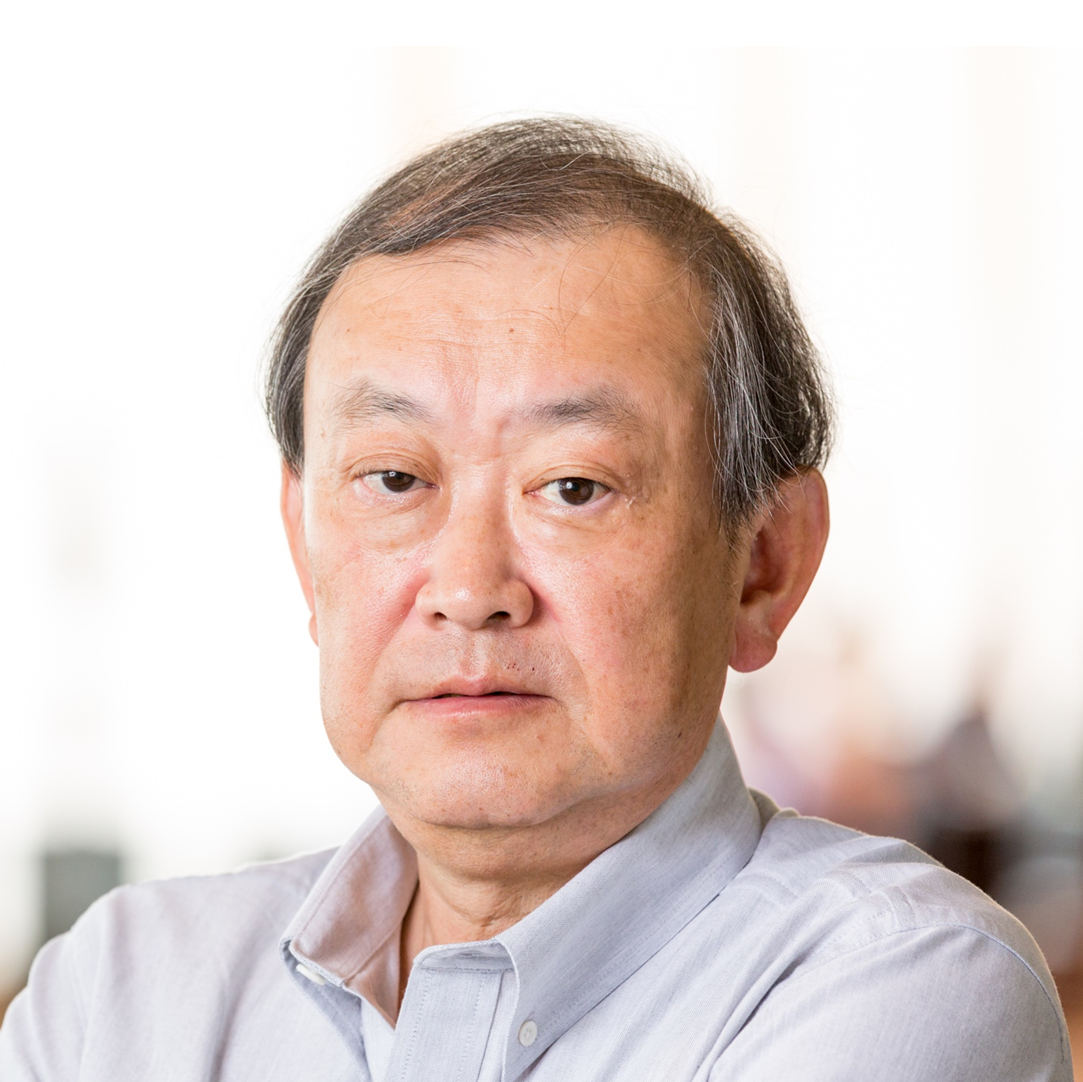前編では、Web2.0の白書「What is Web2.0」(2005年)の登場前後のインターネットの世界について、私の体験談とともにそのときの衝撃を振り返りました。確かにWeb2.0は13年経った現在のインターネットサービスにおいても役立つことが多く書かれています。しかし、この13年間にインターネット業界で起きた事象を知らずにWeb2.0を盲信し、新しいサービスを生み出したとしても、必ずしも上手くいくとは限らないでしょう。
後編では、Web2.0の発表から現在までにインターネット業界で実際に起きたことを振り返りながら、Web2.0の予言の各キーワードが意味するところを私なりに紐解いていきたいと思います。
1.ロングテール(Long Tail)
この言葉の元になっているのはイギリスの経済学者ヴィルフレド・パレートによって提唱された統計的な経験則「パレートの法則」で、「2:8の法則」とも言われています。実社会で商品を売上順にならべたときにヘッド(上位)20%の人気商品が売上全体の80%を占め、残りのテール(下位)80%の不人気商品は全体の売上の20%にしか寄与していない、というものです。通常、実社会ではヘッドに注目・注力するのですが、インターネットにおいてはその法則が当てはまらない場合があります。インターネットではテールの売上がヘッドを超えることもあり得るため、テールも重要だというのです。というのはインターネットにおいては、このテールがものすごく長いロングテールになることも可能だからだというのです。では、テールに注力してインターネットサービスを提供すれば誰もが成功できるのでしょうか?
テールのサービスで成功するには、「ユーザーセルフサービス」であることが大前提です。すなわち、テールに対してのトランザクション処理がほぼ自動化されており、サービス提供者の人手を含めたコストをほぼゼロにしないとビジネスとしては成立しません。そうでないと負担や在庫ばかりが増え、いずれ立ち行かなくなってしまうでしょう。
またWeb2.0では、広告業界のヘッドをターゲットとし、Web1.0企業と言われたDoubleClickと、テールをターゲットとしたWeb2.0企業のGoogle AdSenseの対比がありました。しかし、実はその後Web2.0のGoogleがWeb1.0のDoubleClickを買収するという、広告業界では驚くべき事件が起こりました。「ヘッド」のWeb1.0が古くてダメで、「テール」のWeb2.0は次世代で正解というわけではなく、どちらもバランスよく持った方がビジネス的には成功するのではないだろうかと感じています。
2.永遠のベータ版(The Perpetual Beta)
ネットサービスは24時間365日利用者と接触しているため、ひとたびリリースされると基本的にサービスを止めることは許されません。そのためパッケージソフトの作り方と比べると、根本的に開発手法が異なる点が多くあり、その開発手法やリリース手法もネットサービスに向けたものが求められます。ゴール(最終完成)を設定し、設計・開発と長い時間をかけて完成へと進めていくウォータフォールという開発手法に対し、ネットサービス開発ではゴールを先に設定せず、開発サイクルを極端に短くしサービスを常に進化させる開発手法としてアジャイルが注目されました。確かにサービスを常により良く進化させるためにABテストなどを繰り返す場合は、アジャイル開発手法が向いているでしょう。
しかし、ネットサービスは皆アジャイルで開発するべきなのでしょうか?
たとえば外部にAPIを提供しているサービス(いわゆるSaaS)においては、アジャイル手法がときにAPI利用者に対してとんでもないトラブルを招く可能性があります。実際、私もこれで痛い目にあった記憶があります。なぜなら、API利用者が安定したサービス提供を期待しているのに対し、SaaSにおいてはアジャイルによる変更・修正がAPI利用者のサービスに直接影響してしまう場合があるからです。そのようなリスクが2週間ごとに起きるなら、API(SaaS)の利用者はいつも気が気ではありません。これは、ネットサービス=アジャイル開発と短絡視することに危険が伴うことを意味します。
アジャイルのようなショートサイクルで開発を繰り返す手法は、新規サービスを立ち上げる初期段階においてスモールスタートを可能とし、手戻りが少なく、サービスコストに大きな効果を発揮するため、リーンスタートアップに向いているのだと思います。しかし、複数の利用者にAPIで提供するようなサービス(SaaS)は必ずしも早い進化を求めているわけではなく安定サービス提供が第一であるので、十分な設計と十分な利用者へのステージング提供期間を経て進化させるべきものであると思います。
3.集合知(Syndication)
2005年当時、ネットサービスの多くは情報提供側とサービス利用側に分かれていました。しかしWeb2.0白書では、インターネットの特性である双方向性を活かした利用者参加(発信)型のサービス例としてWikipediaを挙げ、利用者参加(発信)型サービスのブレイクを示唆していました。その数年後に、利用者の発信情報がコンテンツ(UGC:User Generated Contents)となるソーシャルメディアという言葉が登場。そして現在の「YouTube」「Facebook」「Line」「Instagram」「Twitter」などの個人向けネットサービスの中心は、ほとんどが「ソーシャルメディア」だと言っても過言ではありません。
ところが、Googleやヤフーなど当時の大手ネット企業は、ソーシャルメディアの普及とビジネスモデルに対しては懐疑的であったと思います。実際に、かつて私が所属していたヤフーでもそうでした。それゆえ、YouTubeやFacebookなど多くのソーシャルメディアサービスは小さなベンチャーから生まれています。ベンチャーは、ビジネスモデルは二の次で、まず自分たちが使いたい、そして多くの人に使ってもらいたい利用者第一主義“ユーザーファースト”の精神でサービス作りをしていったのです。ソーシャルメディアサービスの恐ろしい側面として、先行して利用者を増やしたサービスに後発サービスが追いつくのは至難の業であるという性質が挙げられます。その最たるニュースが「Google+(グーグルプラス)の個人向けサービスの終了」ではないでしょうか。ソーシャルメディアサービスで重要な点は利用者同士の繋がりなので、たとえインターネットで成功したGoogleのような大企業が後発で追いかけてサービスをリリースしても、ベンチャーのサービスに追いつかないことがあるのです。ソーシャルメディアサービスは、利用者が多くて使いやすいサービスに利用者が集まる特性があります。まさにソーシャルメディアサービスこそが、利用者が決める「インターネットの民主化」とも言えるでしょう。
そしてこのようなソーシャルメディアサービスが世の中で受け入れられると、今度はそのサービスのビジネス化が問われるようになりました。ソーシャルメディアサービスは、利用者の膨大できめ細かな行動履歴やUGCのデータがサービス側に集まるため、そのデータを利用し、行動履歴ベースのきめ細かなターゲティング広告を可能にしました。
2005年当時におけるネット利用者の興味・行動履歴収集と言えば、GoogleやYahoo! などの検索窓に入力するキーワードが主流でしたが、今ではソーシャルメディアサービスの方がより細かい行動履歴を収集できるようになり、ネット広告ビジネスの主流をターゲティング広告へと押し進めていきました。こうして集合知から派生したソーシャルメディアサービスは、そのビジネス化(マネタイズ)の壁も乗り越え、今やインターネット上で人々に広く身近に使われる重要なサービスになったのだと思います。
Web2.0の社会的影響
Web2.0の白書はあくまでもインターネットの中の話でしたが、その後、実社会にもおいても様々な影響を及ぼしていると感じています。たとえば、電力自由化です。昔は、電気は膨大な資本をかけた電力会社が作り出したものをコンシューマが供給として受けるという構図でした。今はコンシューマが微力ながらも電気を供給する形であり、まさにロングテール、ユーザー参加型ソーシャルに通じるのではと感じています。
また、配車サービスの「Uber」も同様です。タクシーはタクシー会社が供給するもので、コンシューマは利用するものとしか疑わなかったものを、コンシューマがサービス提供者に回るのも、一種のユーザー参加型ソーシャルだと感じています。
そう考えると、今は“サービス提供者側と消費者側に分かれている”実社会のビジネスモデルが崩れ、“消費者自身がサービス提供者に回る”新規ビジネスが今後さらに生まれるのでは…、と妄想しています。